
|
国民生活基礎調査によると、1世帯当たりの平均世帯人員は2.95人で3人を切るに至り、家族規模が一層縮小化していることが明らかになっています。(図10)
これは、若年層の一人世帯、中年層の二人世帯が増えているためですが、その背景には、近年の出生率低下による少子化傾向に加え、第二次ベビーブーム世代が進学、就職や結婚などで新たな所帯を形成する親離れ年齢を迎えていることも影響しているとみられます。
さらに、核家族世帯の中でも夫婦のみの世帯が増えており、特に65歳以上の夫婦のみの世帯が著しい上昇傾向を示しています。
長寿化により結婚期間が長期化し、少子化と核家族化により高齢夫婦のみの世帯が増えているのが現代の家族構成の特徴といえますが、結婚期間の推移をみてみると、実際に結婚期問が50年以上となっている夫婦は昭和30年(’55)の20.2%から、昭和60年(’85)年の30.3%へと大幅に延びています。(表10)
また、親子期間が長期化するなかで、65歳以上の高齢者と子の同居率がどのように変化してきたかをみると、昭和50年(’75)には68%であった同居率が平成6年(’94)には55.3%にまで低下してきています。
このように、高齢化と出生率の低下や少子化により、わが国の家族形成と家族構成にも大きな変容が生じてきており、人間社会の基本的な構成単位である家族は、さまざまな要因がお互いに影響し合いながら変容してきています。
図8 世帯数および平均世帯人員の平均推移
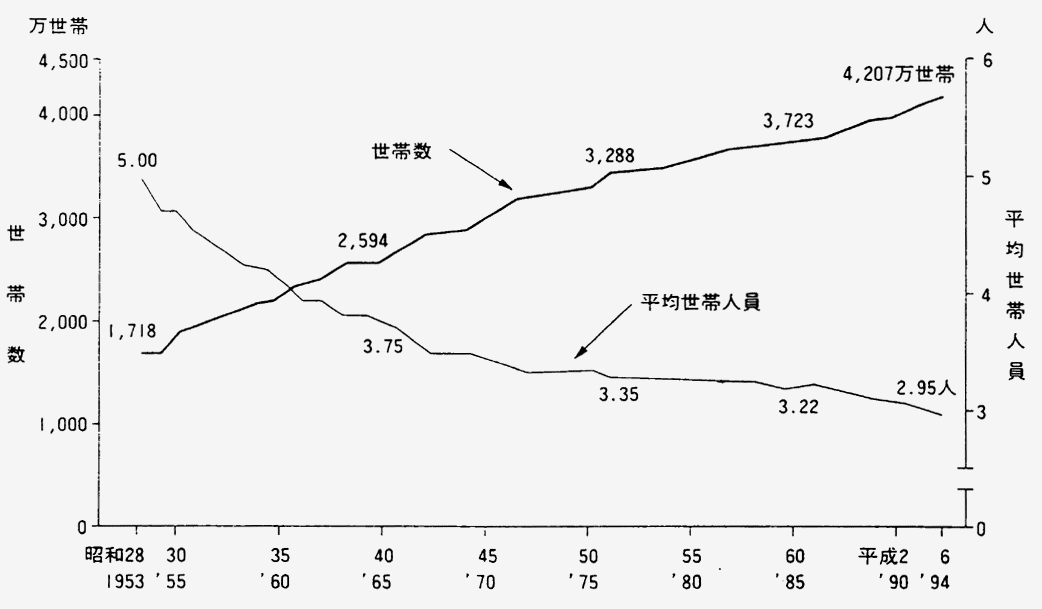
前ページ 目次へ 次ページ
|

|